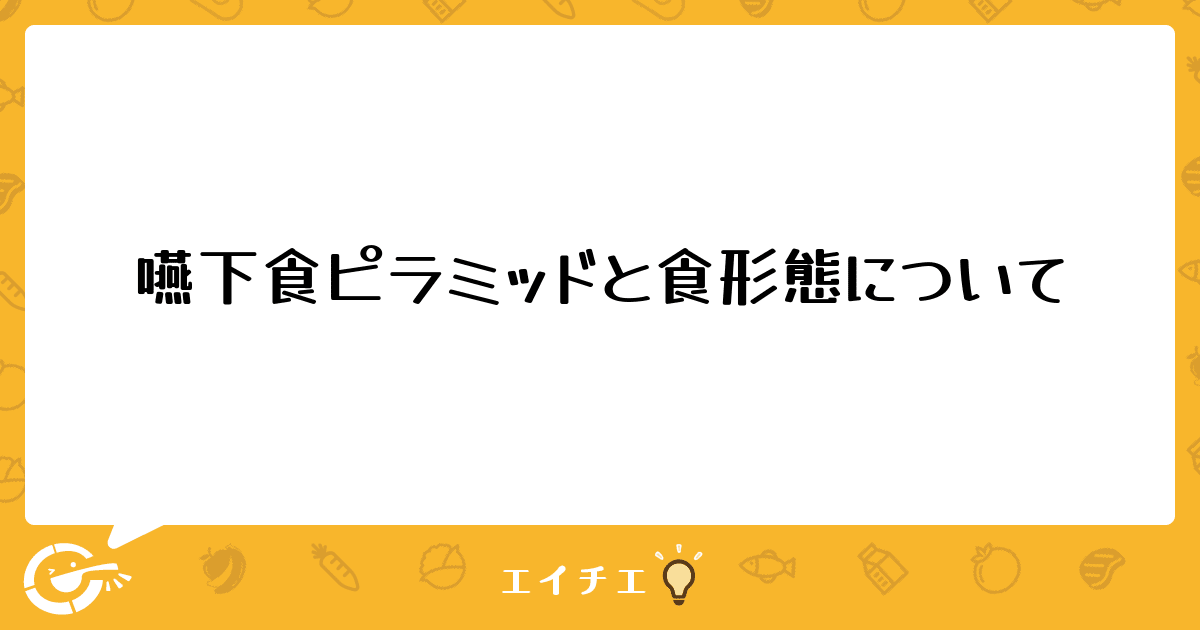60床の療養型病院に勤務している者です。
最近はPEGの方が増え、食事は30~35食程度を作っています。
現在の食形態は
形・軟菜・きざみ・ソフト・ミキサーの5種類です。
食事の事は主に、病棟の歯科衛生士さんと話し合って決めていくことが多いです。
歯科衛生士さんは、嚥下食ピラミッドが全国的に流通してるから当院も嚥下食ピラミッドを用いるべきと言う考え方です。
それができればいいのでしょうが、35食のうち、嚥下食対応の方(ソフト・きざみ・ミキサー)は12名です。
これらを嚥下食ピラミッドに当てはめるとなると、現状では既製品を使用するしかないかなと思います(マンパワー・設備不足)。
ただ、歯科衛生士さんは嚥下食ピラミッドをそのまま適用させるのではなく、食形態を現状の5段階→6段階にすることを意味しているようです。
となると、嚥下食ピラミッドとは関係ありませんよね?
歯科衛生士さんは、現在の「軟菜」が問題だと言われています。
当院の軟菜と形食の差があまりなく、繊維質の野菜やきのこや海藻類を除く程度です。
特に肉と魚が問題で、豚肉のスライス・ささみ・・・何を使っても硬いと言われます。
一度、「あいーと」と言う、酵素で軟らかいが形がしっかりと残している既製品を試食したら、そちらに感動されそれを軟菜の次の「移行食」として使いたいそうです(-_-;)
ただ、金銭的には無理です(1製品あたり500~600円)。
皆様の施設での食形態は何段階位に分けて有りますか?
また、軟菜の肉・魚はどのようにして使用されていますか?
軟菜食とは別に、移行食という区分を設けて有りますか?
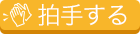
※こちらの質問は投稿から30日を経過したため、回答の受付は終了しました
2人が回答し、0人が拍手をしています。
1/1ページ