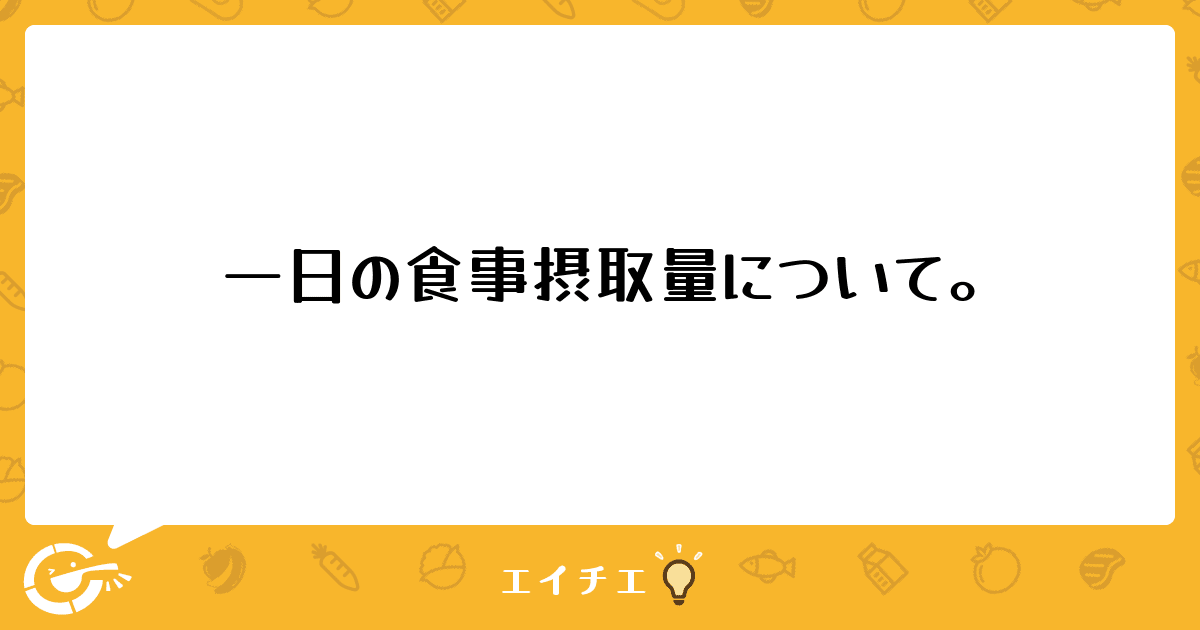- TOP
- お仕事Q&A
- 介護・福祉施設
- 栄養ケアマネジメント
知的障害者施設に勤務しております。
私の施設では、食事は、寮毎に配膳車で配膳しています。
ご飯は、おひつに、寮の人数分を入れ、寮で介護職員がお茶碗に盛って配膳しています(計量はしていません)。
寮の職員曰く、利用者さんの調子を見て、ご飯の提供量を毎食多少変えている、ということです。
4月から、栄養ケアマネジメントを開始するにあたり、個人の正確な提供量・摂取量を把握するため、おひつでの提供を廃止し、厨房で一人ひとりお茶碗に盛って配膳するのはどうか、ということを寮の職員(介護職員)に聞いてみました(主食の摂取量が100%だとしても、200gよそったものなのか、300gよそったものを食べてなのか分からないのではないかという例を挙げました)。
職員の回答は、「食事摂取量調査は、一日の摂取平均を見るのだから、例えば、こだわり等で朝食・昼食を食べなければ、夕食で少し量を多めに提供しても、一日平均として考えるのだから、良いのではないか。そういう微調整を行うために、おひつで配膳する方が良い。」というものでした。
要するに、極端な話し、ドカ食いでも一日平均すれば大丈夫、ということになります(ちょっと極端ですが)。
一方的に言われてしまったので、私は「そうですか。」としか言えませんでした。
でも、栄養ケアマネジメントを行う上で、きちんと管理していないと、体重が安定せず、ケア計画に誤差が生じてしまうと思うのですが…。
私は、食べられない分を食べられる所で補うよりも、なぜ食べられないのか、その原因を探り解決するのが介護職員のすべきことではないかと思います。
しかし、こだわりがあったり、食が細かったりする人は、このように一食の量を増やすことも、許容すべきなのでしょか。
よく耳にする"時間栄養学"的にも大丈夫なのでしょうか。
私は、考えが堅すぎですか。
どなたか教えていただけませんか。よろしくお願いいたします。
※補食のことは抜かして、三食だけの話しでご回答下さると嬉しいです。
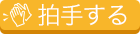
※こちらの質問は投稿から30日を経過したため、回答の受付は終了しました
4人が回答し、0人が拍手をしています。
1/1ページ