加工食品の開発職についています。
商品開発をする際に、味の濃さ等をを把握するために塩分を計算することがあります。
その際、食塩分と食塩相当量のどちらを目安にしているのか、ご意見をいただければと思い質問いたします。
メーカーからの規格書を見ますと、モール法による食塩分とナトリウムからの食塩相当量でかなり差があるものがあります。
例えば、いま手元にある醤油の規格書ですと、食塩分は15.5%、食塩相当量は13.3gです。
この醤油のほかに数種類の調味料(味噌や昆布エキス、グルタミン酸ナトリウム等)を配合して「たれ」を作る場合、商品設計の参考にする値はどちらを使用するのがよいでしょうか。
品質管理的にはモール法を用いるかと思いますが、栄養士的には食塩相当量かなと思ったりもします。
しかしナトリウム量から計算すると、グルタミン酸ナトリウム等を添加する場合は実際に感じる塩味より高値になることも多く、どちらが良いのか迷っています。
商品開発の際に参考にするのは、理化学試験の食塩分、栄養成分の食塩相当量、どちらでしょうか?
どちらも、という方はどのように使い分けていらっしゃいますか?
理由もぜひお伺いしたいです。
よろしくお願いいたします。
3
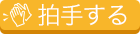
※こちらの質問は投稿から30日を経過したため、回答の受付は終了しました
2人が回答し、0人が拍手をしています。
1/1ページ
 同じカテゴリの新着の質問
同じカテゴリの新着の質問
722
3
16
2025/10/24
703
1
0
2025/08/12
965
1
3
2025/08/01
1698
4
13
2025/07/28
1071
1
1
2025/06/19
1045
2
5
2025/06/08


,w_1000,c_fit,h_200,y_-40/v1622682157/eichie_ogp_orange_bg_nt_20210603_xmn4yd.png)




