いつもお世話になっております。
特養です。
かきこんで食べる人、よくあるリスク行動だと思いますが、
そういった方に対する対応方法がいまいちハマらないと感じ、
常日頃悩んでいます。
他の栄養士さん達はどう考えるのか意見を伺いたく投稿しました。
うちの施設の利用者様の事例です。
男性、自立摂取、箸使用。食事摂取における身体機能の問題はなし。
傾向:一口量多め、何口か詰め込んで口いっぱいにする。
その後手を止めて咀嚼しばらくする。結構長く咀嚼。その間は
食べ物を口に入れない、途中水分を(汁や茶)補給し嚥下。
その後、再び口にいっぱいいれる。繰り返し。
対応1:声かけ
基本的な対応ですが、そもそもこれで直せる人は問題にならない。指示が入らない、言っても聞く気がない、習慣なので直せない事がほとんど。食事中に食べ方を何度も注意されるのも気分的に嫌だし集中できないのではと個人的には思う。
対応2:小分け
一口ずつ提供するわけにもいかない。小鉢一杯くらいづつ出すがそれを全部口に入れてしまわれれば同じ事のような気がする。途中でやめることもせず全部かきこもうとする人には有効かもしれないが、この方は途中で休むのであまり意味はないと思う。
対応3:小さいスプーン等の食具
一口量が多く、かきこまない人には有効だが、かきこむタイプの人だと結局入れる回数が増えたりお椀から直接口に流し込んだりして口に入る量が変わらない。食べこぼしの率も上がる事が多い
対応4:食事介助
他サイトでそういう対応していると書いてある物があったが、自分で食べられる人に介助するのはいろんな意味でどうかと思ってしまう
対応5:形態を小さく刻む
喉つまりのリスクは減らせるかもしれないが、咀嚼できる人から咀嚼を奪うこともどうかと思ってしまう。誤嚥の可能性は逆に高くなるかもしれない事も気になる
長くなってしまい申し訳ありません。
全て個人的な意見ではあります。間違っているかもしれません。
皆さまはどうお考えになるでしょうか。
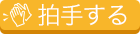
※こちらの質問は投稿から30日を経過したため、回答の受付は終了しました
1人が回答し、0人が拍手をしています。
1/1ページ






