保育園で栄養士をしています。
野菜など、調理をするとカサが減り、生の状態よりもg数は減ると思います。
しかし、なぜその減る分を足さないのか。
例えば、ほうれん草50gが茹でたら40gになった。
50gが摂取するべき量なら50gが口に入るように分量を増やさなくてはならないのではないか?と保育士から質問がありました。
生のほうれん草50gが茹でて量が減ったとしても50g分の栄養価として計算しており、増やしてしまうと栄養価も変わってきてしまいます。
本当は減る分を見越して多目の分量に設定するべきなのでしょうか…?
それとも栄養計算をするとき、「ほうれん草 ゆで」といった実際に行う調理法で栄養計算するべきですか?
0
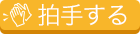
※こちらの質問は投稿から30日を経過したため、回答の受付は終了しました
2人が回答し、0人が拍手をしています。
1/1ページ
 同じカテゴリの新着の質問
同じカテゴリの新着の質問
145
1
0
2026/01/14
167
1
0
2026/01/09
190
1
1
2026/01/08
367
1
0
2025/12/11
487
1
1
2025/12/10
719
1
0
2025/11/05
 ランキング
ランキング
145
1
0
2026/01/14







