特養に今年1月から勤めている20代管理栄養士です。
多職種連携を要請する際の、見極め?考え方?について悩みがあります。
●皆様は、入所者様がどういった状態になったら、口腔・嚥下評価やポジショニングの確認の依頼をすることにしていますか?
以下は、質問するに至った理由です。
やや愚痴のような、長文になりますが、ご意見等いただけると助かります。
入所者様の食事の様子を日々観察していて、
姿勢が悪く食べづらそうにしている・激しいムセが見られる・いつまでも口に溜め込んでしまう、といった様子が継続して見受けられる方々が居ます。
このような状況を見ていると、食形態や、姿勢、食事環境など改善できる所は無いか、何とかより食事を食べやすくすることはできないかと気になってしまい、
同法人内老健のPTやST、歯科衛生士に口腔・嚥下評価やポジショニングの確認を私から度々依頼することがあります。(皆さん快く引き受けて下さっています。)
そうした中、特養相談員やナース、介護士に評価依頼しようと思っていることを相談すると、
「その方(まだ自力摂取・椅子に座って食べている方)は、家族から今後食べられなくなった時の看取りの許可を戴いてるし、あんまり診てもらわなくても良いんじゃない?」
とか
「もう歳なんだし、姿勢だとか、口腔がどうとかの問題じゃない気がするんだけど?(精神薬調整や検査など何度もしているが原因がハッキリしないまま、ムセや溜め込みが直らない方、まだ看取りの診断などもありません)」
といった風に、
反対意見を都度言われます。
私としては、食事が上手く食べられない原因を、多職種に診てもらうことで手懸りを見つけて少しでも改善できればと思ってのことなのですが、
他の方々が言うように私が一々変なところで気にしすぎているのか?
特養であるならば、ある程度自由に、自然のままにしておく方が正しいのか?
誰でも彼でも診てもらいすぎなのか?
とぐるぐる思い悩んでいます。
どうかご意見よろしくお願いいたします…。
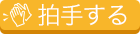
※こちらの質問は投稿から30日を経過したため、回答の受付は終了しました
5人が回答し、0人が拍手をしています。
1/1ページ








