厚生局の監査で食材の発注方法を指摘されました。
42床(一般20床、療養22床)の病院勤務です。労務委託なので他に栄養士はいません。
調理食の提供食数は、患者は朝昼夕それぞれ7~15人(1日の増減は0~3人程度)、職員は平日の昼のみ4~6人です。職員食は常食と同じものを出しています。基本的な発注食数は朝夕15食、昼20食で、患者食が少ないときには発注量を調整しています。
現在は発注書に患者食と職員食の合計kg数、そこから20~25%を職員分として使用する旨を記載しています。例えば、発注書(栄養士作成)は「大根1kg(職員20%)」、納品書(商店作成)は「2本」、請求書(栄養士作成)は発注書と納品書を照らし合わせて「患者1.6本、職員0.4本」というように案分しています。町内の個人経営の商店から購入するので、生鮮品は規格が決まっていないため、2本など個数での発注はできません。
調味料や油、米、冷凍食材は規格品なので個数発注です。例えば「醤油1本(患者0.8本、職員0.2本)」というように案分しています。
厚生局からは、調味料も含めて案分するのではなく、発注の時点でしっかり分けるよう指導されました。監査官は発注のことしか言いませんでしたが、調味料も別というのであれば、調理も別にしなければならないのか、一緒でも良いのか解りません。別なら調理員も調理器具も不足です。
生鮮品は納品されるまで大きさ、量、価格が解りません。人口3000人程の町なので、商店は最低限の商品しか置かず、1/2カットなどの野菜は販売していません。大根やキャベツなどの大きい野菜は職員食で使えなくなります。調味料も使い切る前に傷むか、期限切れになると思います。
病院の都合で商店に負担を求めることは難しいです。
このような状態で、案分以外に方法はあるのでしょうか?
病院の規模から見て現実的でない指導をされて困っています。今月分は仕方ないということで、4月分からの改善内容をあと1週間で提出しなければなりません。アイディアがありましたら、よろしくお願いします。
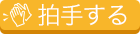
※こちらの質問は投稿から30日を経過したため、回答の受付は終了しました
2人が回答し、0人が拍手をしています。
1/1ページ






