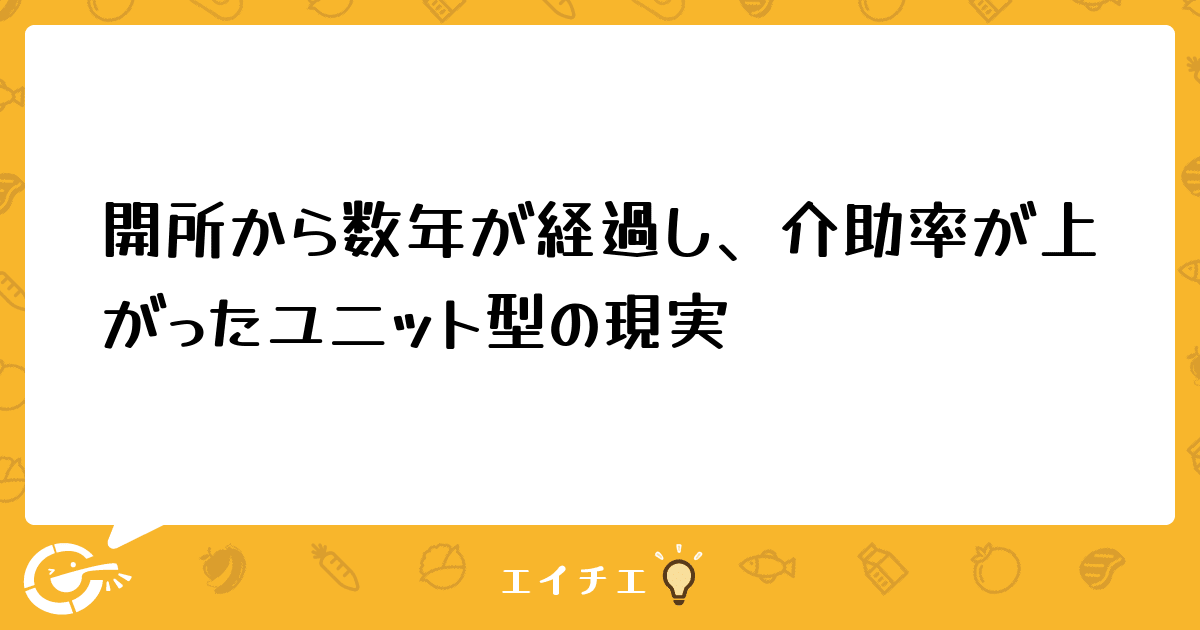開所から数年たって、1ユニットあたり多いと6人が食事介助と
いう状態です。
数分に一度の声掛け程度から全介助までありますが、朝と夕の
食事介助の手が足りないユニットがちらほら増えてきました。
今経口復帰訓練中の方が本格的に食事に移行すると、異食盗食リスク
が高い方なのでつきっきりになります。
絶対不可能、とスタッフから食事復帰を拒否られてまいりました。
条件としては栄養士と看護師が毎食立ち会う、これまた無理な話。
平日短時間だけのパートさんが多くて、常勤で朝と夕の介助を
全部回すのは大変。だからって食べられる方に食べさせないっていう
選択肢はないでしょう・・・
改めてカンファレンス予定ですが、激闘になりそうです。
常勤換算人員は満たしてるから、食事の時間にさらにスタッフを増やすのは無理。と言われているので、ケアマネ・栄養士・相談員・看護が総出で食事の時間に各ユニットに散ることになるんでしょうけれど、最近事務室系も退職があって補充がなく、気づけば私だけ事務室に一人・・・ということも少なくないので、簡単に手伝いにいける状態でもなく。
施設内どこもかしこも人手不足です。
開所から10年近くたったユニット型施設が近場にないので、他の
施設の参考例もなく、どうやって回していくのかな、と不安です。
介助度が上がってしまって、ユニット単位で処理しきれなくなった
ときどうするんでしょうか。
案としては、重介護ユニット、を作って手厚い配置と手薄な配置を使い分ける、など上がってますが、手薄なユニットに
回せる入居者を洗い出してみると数人しかいません。みんなある程度の
リスクを持っています。
大人しいけど全介助。ADL自立に近いけど転倒リスク高い。盗食しそう。
どうやってうまく回して、介助度が上がっていく入居者を問題なく
安全に、そして理想の「その人らしい介護」を実現していくのか。
壁にぶち当たっています。
いい知恵をお持ちの方、経験談などあればお教えください。
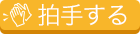
※こちらの質問は投稿から30日を経過したため、回答の受付は終了しました
4人が回答し、1人が拍手をしています。
1/1ページ